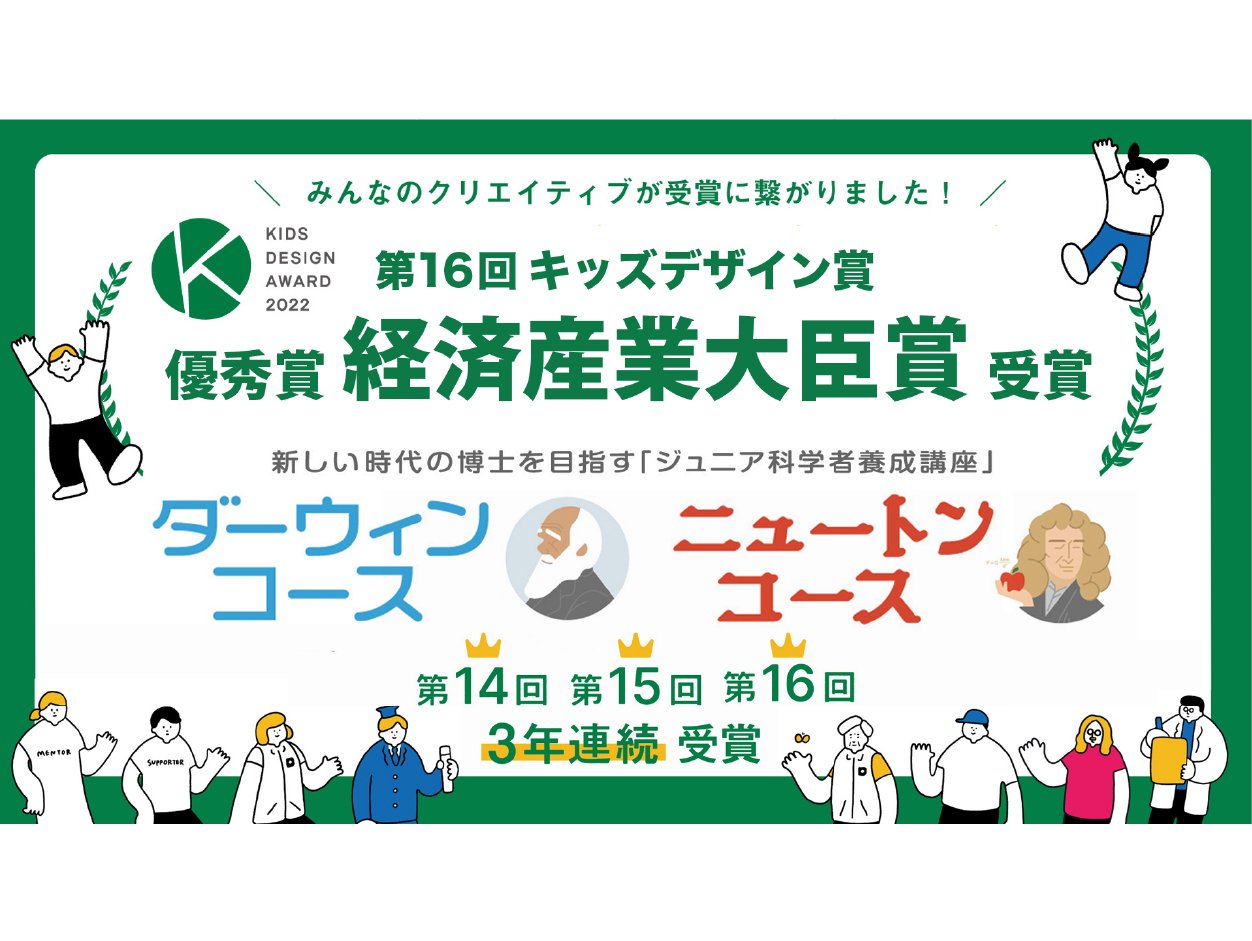[開催終了]実践から科学する力を養う「ジュニア科学者養成講座」―ダーウィンコース― 【2025年4月開講】

2025.04.27 ~ 日曜日 13:00
[開催終了]実践から科学する力を養う「ジュニア科学者養成講座」―ダーウィンコース― 【2025年4月開講】
福岡市科学館 / 九州大学伊都キャンパス 他 / スペシャル企画

INDEX >> 「ジュニア科学者養成講座」-ダーウィンコースとは? / 開催概要
「なぜ?」「どうして?」とたくさん出会う
科学者になるには、たくさん勉強して、さまざまな知識を身につけることが最も重要でしょうか。たくさんの知識は科学の研究に役立ちますが、知識があっても科学者になれるわけではありません。科学者になるためには「疑問を持つ力」を育むことが大切です。また、未来を創造する科学者になるためには、探究心や知的好奇心、疑問を研究するための発想力や勘などの「科学する力」を養うことが必要です。この講座では科学館外のフィールドや実験室で、五感を働かせながら様々な体験をし、チームで協働しながら体験で得た学びを表現します。このような実践を通じて「科学する力」を身につけてもらうのが「ジュニア科学者養成講座」です。
プログラムの紹介〜教わるのではなく体験で身につける〜
ダーウィンコースは、生命科学・人間科学・環境科学の3つの視点から、科学の楽しさを伝え、科学への道案内をするプログラムです。森や川で出会う生きもの、生きていくための食、より住みよい暮らしをするために開発した街を知り、人間は森に暮らしていたころから現代へとどのように変化していったのかを考えます。講座を重ねるごとに「人間らしさ」の謎に出会うことができます。このようにたくさんの実体験を通して、みなさんならではの感性で人類の進化について考えていく旅が、ダーウィンコースです。
見つけたこと、気づいたことを一緒に参加する仲間と共有したら、チームで表現を行い発表します。チームで作品を完成させるためには、自分の考えを伝えるとともに、相手の考えをよく聞くことが求められます。生じた問題を解決するためにアイデアを出し、工夫してもうまくいかないことがあります。さらに工夫を加えたり、その失敗や挫折を糧にしたりすることによって人は成長します。
このプログラムにより、意欲、自信、忍耐、自立、自制、協調、共感などの様々な心の部分が成長します。これらはテストの結果のように点数化することが出来ない「非認知能力」と呼ばれるものですが、参加者が見せてくれる表情と行動に、「成長の証」を読み取ることができます。
「本講座」+「探Qゼミ」で構成
ダーウィンコースは、フィールドワークや実験を行う「本講座」と、講座内容を振り返り表現を行う 「探Qゼミ」のセットで実施します。「本講座」では自然のフィールドや実験室で、研究者と一緒に普段できない経験をします。そこで生まれた気づき、興味、疑問を「探Qゼミ」で持ち寄り、グループでコミュニケーションを重ね、ひとつの作品としてまとめ表現します。この一連のプロセスの繰り返しにより、未来を創造するために必要な力が育つと考えています。
幅広い分野の講師陣と福岡市科学館のサイエンスコミュニケーターが子どもたちの好奇心をサポート!
この講座は、九州大学の科学の専門家(九州大学教員と大学院生)、デザインの専門家(九州大学芸術工学院の教員と大学院生)、コミュニケーションの専門家(科学館のサイエンスコミュニケーター) が共に考え開発した講座です。また、九州大学教員によって設立された一般社団法人九州オープンユニバーシティの研究者・スタッフと、九州大学の大学生・大学院生の協力を得て、毎回改良を加えながら実施しています。
「キッズデザインアワード2022」で優秀賞を受賞
「ジュニア科学者養成講座(ダーウィンコース&ニュートンコース)」は、「キッズデザインアワード2022」の「こどもたちの創造性と未来を拓くデザイン部門 クリエイティブ部門」において、優秀賞(経済産業大臣賞)を受賞しました。「非認知能力を高める教育」や「STEAM教育」が時代の要請として求められているなかで、これらを習得するための良質な素材となり、先入観にとらわれない、自由なクリエイティビティを伸ばす総合的講座である点を高く評価した。先入観にとらわれない、自由なクリエイティビティを伸ばす総合的講座である点を評価していただきました。受賞についての詳細はこちらをご覧ください。
\ こんな人におすすめ /
・植物や生きものに興味がある
・将来研究者になりたい
・自分で考えたことを伝え、みんなと共有したい
・九大の先生や専門家にたくさん質問してみたい
・大学でどんな研究が行われているか興味がある
・さまざまなものの見方にふれたい
・「なぜ?」「なんだろう?」を追求したい
過去の活動の様子
※今年度は内容が異なる場合がございます

チラシ (クリックするとPDFで開きます)

開催概要
- タイトル
-
実践から科学する力を養う「ジュニア科学者養成講座」
―ダーウィンコース― 第3期
- 講師
-
九州大学などの多彩な講師陣と福岡市科学館のサイエンスコミュニケーターが子どもたちの好奇心をサポート!
[第1回 森の回・第3回 街の回]
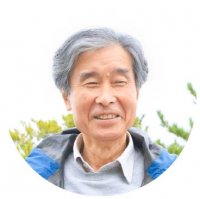 ■
■
矢原 徹一
(福岡市科学館 館長/九州大学大学院理学研究院 名誉教授/一般社団法人 九州オープンユニバーシティ 理事)
専門は生態学・進化生物学。著書に『花の性―その進化を探る』(東京大学出版会)、『保全生態学入門─遺伝子から景観まで』(共著、文一総合出版)など。ももクロは紫推し。
 ■
■
吉村 友里 氏
(九州大学 工学部・学術研究員/九州大学 理学部・研究員/一般社団法人 九州オープンユニバーシティ・研究員)
専門は、生態学・動物行動学。両生類や爬虫類を対象に、動物が出す"におい"が敵への警告シグナル(警告臭)としてどのように働くのかを、化学分析も使いながら研究しています。最近は生き物の保全にも関わっています。推しはツチガエルですが、嗅ぎすぎてアレルギーを発症し、くしゃみが止まりません。思い切り嗅げないのが悩みです。
[第2回 川の回]
 ■
■
鹿野 雄一 氏
(一般社団法人 九州オープンユニバーシティ・理事)
専門は魚類学・河川生態学。おもに福岡県と熊本県で、いろんな淡水生物と現場で向き合っています。近年は生物の3Dモデル化にも取り組んでいます。人生の目標は、できるだけ多くの野生生物と出会うこと。
[第4回 食の回]
 ■
■
比良松 道一 氏
(新潟食料農業大学食料産業学部・教授 /一般社団法人 九州オープンユニバーシティ・代表理事)
専門は農学、園芸学。作物の品種改良に携わる中で、作る人と食べる人がつながることの大切さに気づき、自炊を通じて社会問題を学ぶ「自炊塾」を開講。料理好きな人を増やす活動に取り組んでいます。年に数回、包丁を楽器に持ち替えてライブ演奏活動にも参加しています。
 ■
■
竹内 太郎 氏
(一般社団法人 九州オープンユニバーシティ・研究員 / 福岡公立古賀竟成館高等学校非常勤講師)
専門は、日本近代思想史(沖縄民衆思想史)です。沖縄の言語学者・伊波普猷(1876-1947)についてテキスト分析を通して、その思想を研究しています。また、料理研究家としても仕事をしており、レシピ開発や食育授業などを行う傍ら、県内の高校では地理の教員として、食文化や思想史的な知見を盛り込んだ授業を行っています。
[第5回 心の回]
 ■
■
錢 琨 氏
(九州大学 アジア・オセアニア研究教育機構・准教授/一般社団法人 九州オープンユニバーシティ・理事)
専門は心理学。実験や質問紙調査などの手法を使って,知覚(錯視)から感情・性格まで幅広い心理学的事象について研究しています。最近のブームは「フィールドワーク×心理学実験」。フリーランスデザイナー。趣味は旅と料理です。
[後期 アリの回]
 ■
■
村上 貴弘 氏
(岡山理科大学 理学部・教授/一般社団法人 九州オープンユニバーシティ・理事)
専門は保全生態学、行動生態学。九州大学ヒアリ研究グループ代表。1993年よりパナマ共和国でハキリアリの研究を続ける。いま、一番力を入れているのが、アリの音声コミュニケーション。みんなでアリ語を話しましょう!
[探Qゼミ]
 ■
■
平井 康之 氏
(九州大学 大学院 芸術工学研究院 教授)
専門は、さまざまな人々と一緒にデザインするインクルーシブデザインです。それを応用して、家具などのモノのデザインや博物館などの空間デザインから、ガイドブックなどのコトのデザインまで幅広く活動しています。椅子が大好きで、世界の優れたデザインの椅子を集めています。
- 日時
-
前期:2025年4月27日~2025年10月5日(全11回)
後期:2025年10月中旬頃~2026年3月頃(全10回)
日曜日に開催
スケジュール
第1回 森の回
入学式・本講座 2025年4月27日(日) 13:00~16:00
探Qゼミ 2025年5月11日(日) 13:00~16:00
第2回 川の回
本講座 2025年5月25日(日) 13:00~16:00
探Qゼミ 2025年6月 8日(日) 13:00~16:00
第3回 街の回
本講座 2025年7月 6日(日) 13:00~16:00
探Qゼミ 2024年7月20日(日) 13:00~16:00
第4回 食の回
本講座 2025年8月10日(日) 13:00~16:00
探Qゼミ 2024年8月24日(日) 13:00~16:00
第5回 心の回・人類史の回
本講座Ⅰ 2025年9月 7日(日) 13:00~16:00
本講座Ⅱ 2025年9月21日(日) 13:00~16:00
探Qゼミ・終了式 2025年10月 5日(日) 13:00~16:00
※状況により日時が変更になる場合がございます。
※各本講座と探Qゼミの間に親子で取り組む宿題:「ミッション」が出されることがあります。
※後期の日程・内容の詳細は、改めてお知らせします。
※後期の本講座はフィールドワークではなく、実験やワークショップなどを実施します。
- 場所
-
福岡市科学館 / 九州大学伊都キャンパス 他
※各会場までの交通費は各自ご負担いただきますようお願いいたします。
- 対象
-
小学4年生~小学6年生と保護者
※2025年4月時点での学年表記です。
※親子でご参加いただくプログラムです。
- 定員
- 15組30名
- 参加費
-
この講座は、1年を通した講座ですが、前期と後期に分けて実施します。
後期は、前期受講者のみ申込可能です。
1組2名(親子)
前期 30,000円 (税込)、後期 30,000円 (税込)
[支払い方法] 口座一括振込
[振込期限] 前期分 2025年4月22日(火)まで
後期分 前期終了式にてご案内いたします。※別途振込手数料がかかります。振込手数料は参加者負担となります。
※振込方法等の詳細は、選考結果通知の際にご連絡させていただきます。
※期限を過ぎても振り込みがない場合は、キャンセルとみなします。
※領収書はご利用銀行の振込領収書をもって代えさせていただきます。
※振込の証明書等は必ず保管をお願いします。(当館で振り込みが確認できない場合、振込の証明書等をご確認させていただくことがあります。)
※期の途中で退会される場合、お支払いいただいた参加費は返金できません。
- 選考方法
-
作文による選考
「私のとっておきの疑問」(生きものや植物に関する疑問や質問)について作文してください。
疑問を持ったきっかけやエピソードがあれば書いてください。
※ページの最下部に表示される申込フォームにご入力ください(200字~400字)。
※お子さま自身が作文してください。
※本講座で、作文の疑問について調べるわけではありません。
初級コースでは疑問を持つことを大切にしているため、このような課題にしました。
- 申込方法
-
ホームページより事前申込制です。
留意事項を必ずご確認のうえ、ページの最下部に表示される申込フォームよりお申し込みください。
応募者数が定員を超えた場合は、選考にて参加者を決定します。
申込受付期間
2025年3月15日(土)12:00(正午)~ 2025年4月8日(火)18:00
選考結果通知
2025年4月16日(水)20:00迄に、応募者全員にメールで結果をご連絡します。
留意事項
・申込フォーム入力前に「@fukuokacity-kagakukan.jp」の受信ができるように設定をお願いいたします。確実なメール受信のため、ドメインを指定して受信されることをお勧めしております。ご自身が設定されていなくても、使用しているメールの初期設定などにより、自動返信メールが受信できない場合があります。ドメイン指定受信やメールフィルター機能などを使って、「@fukuokacity-kagakukan.jp」の受信設定をお願いいたします。
・申込フォームをご入力・送信完了後、当館よりお申し込み完了の自動返信メールをお送りいたします。
・申込フォームで「お申し込みが完了しました」と表示された時点で、お申し込みは完了いたします。
- 活動ポイント
-
ポイントの付与はありません。
※ファンクラブに入会して講座や実験に参加すると「活動ポイント」を集めることができます。また、活動ポイントを貯めるとさまざまな得典と交換できます。
ファンクラブ利用案内を詳しくみる
- 免責事項
-
福岡市科学館(以下、「当館」といいます)は、ジュニア科学者養成講座(以下、「本講座」といいます)の運営にあたり、下記の各条項に定める事項については、免責されるものとします。
本講座を受講いただく方(以下、「受講者」といいます)は、本免責事項の内容をご承諾頂いたものと見なしますので、ご了承ください。
1. 当館は、本講座の内容変更、中断によって生じたいかなる損害についても、一切の責任を負いません。
2. 当館は、受講者の都合によって本講座を受講できなかった場合について、一切の責任を負いません。
3. 当館は、本講座を受講したことにより直接的または間接的に受講者に発生した損 害について、一切賠償責任を負いません。ただし、当該損害が当館の故意または重過失により発生した場合は除きます。
4. 当館は、受講料入金手続後の受講料の払い戻し(返金)について、一切受け付けません。
- その他
-
・当館スタッフが、講座の模様を撮影します。これらの撮影物(写真・動画等)は、当館の活動報告として、公式ホームページや公式SNS、各種印刷物等に使用・掲載させていただくことがございます。予めその旨、ご承諾願います。
・講座の中で作成したものにつきまして、福岡市科学館の広報活動(HP、SNS、広報誌等)や活動の報告で使用させていただく可能性がございますので予めご了承ください。